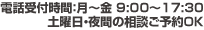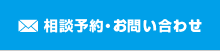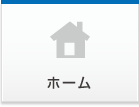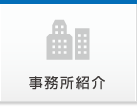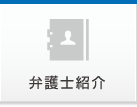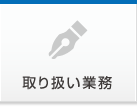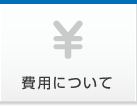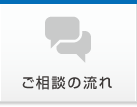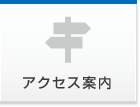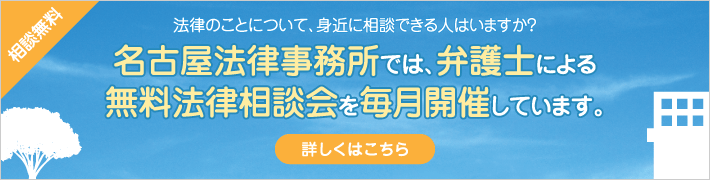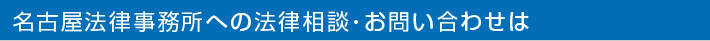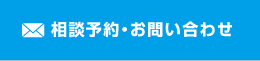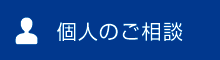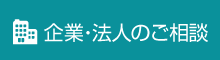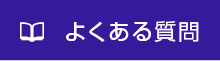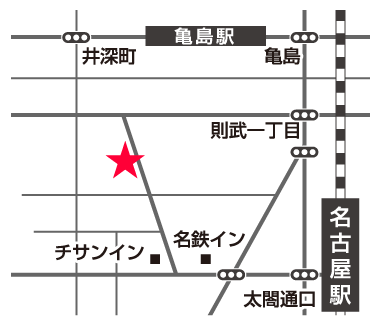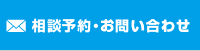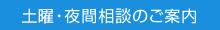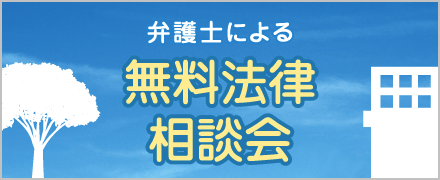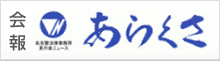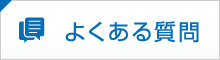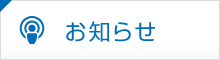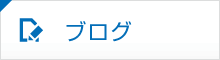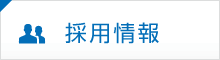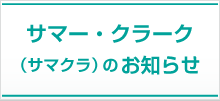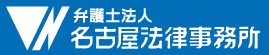スタッフブログ
改正相続法のお話 その2 ―2020年4月1日から施行される配偶者居住権の制度とは?―
<相続に関する法律の一部改正>
相続法制の見直しに関する「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年法律第72号。以下「改正相続法」といいます。)が2018(平成30)年7月6日に成立し、同月13日に公布されました。
※当事務所のブログでも、以前に自筆遺言証書に関する改正点(改正相続法のお話 その1)に関して取り上げておりますので、そちらもご参照ください。
この改正は、約40年ぶりといわれる大改正で、改正の目的は多岐にわたりますが、改正相続法の主な内容は、概ね以下の6項目に整理されます。
- 配偶者の居住権を保護するための方策
- 遺産分割に関する見直し等
- 遺言制度に関する見直し
- 遺留分制度に関する見直し
- 相続の効力等(権利及び義務の承継等)に関する見直し
- 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
今回は、もうすぐ(2020年4月1日)施行される、上記1.の配偶者の居住権を保護するための方策について、ご説明したいと思います。
なお、本稿は、あくまでも一般論のご案内となりますので、個別具体的な事案についてお悩みの方は、弁護士等の専門家にご相談ください。
<配偶者の居住権を保護するための方策>
被相続人の配偶者が、相続開始時に居住していた建物につき、一定の要件の下に法定の居住権を設定することができるようになります。
(1)配偶者居住権(民法1028条1項)―配偶者の居住の長期的保護
特に高齢の配偶者においては、住み慣れた居住環境での生活を継続するために居住権を確保しつつ、その後の生活資金として、住居以外の財産についても一定程度確保したいと望む場合が多いと思われます。
改正前においても、実務的には、配偶者が居住を続けられるよう建物を相続して取得したり、建物を相続した他の相続人との間で賃貸借契約を締結したりする調整が行われていました。
しかし、建物を相続し、住む場所を確保できたとしても、高額な評価額の自宅を相続したために、それ以外の財産を十分に受け取れず、生活費が不足するなどの不安を抱えることになることがあります。
また、自宅を取得するために他の相続分の持分の代償を支払わなければならないこともあります。代償を支払う用意ができなければ、建物を処分して金銭で分割するよりほかなく、自宅に住み続けることができないことになります。
夫婦で夫名義の自宅(夫名義の土地建物)に長年住んできたが、夫が亡くなり、子ども(一人とします)は既に独立して家を出ているところ、妻は、これまで通り自宅に住み続けたいという例で、具体的に考えてみます。
夫が残した遺産が土地建物3000万円、預貯金が4000万円の総額7000万円であった場合、法定相続分は、妻が2分の1(3500万円)、子どもが2分の1(3500万円)です。
法改正前においては、妻が、自宅に住み続けるために自宅土地建物を取得した場合、法定相続分に従って取得できる預貯金は、500万円です。住む場所はあるけれど、十分な預貯金は確保できず生活に不安を抱えるということになります。
このような場合に、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住権)を設定することができることとしたのが、新設された配偶者居住権の制度です。
この制度によれば、妻は、配偶者居住権(財産的価値が1000万円と評価されたとします)と預貯金1500万円、子どもは負担付きの自宅土地建物の所有権(1000万円)と預貯金1500万円を取得することとなり、妻は、自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できることとなります。
ただし、配偶者居住権の成立のためには、
- 配偶者が、相続開始のときに、遺産である建物に居住していたこと
- 当該建物が、被相続人の単独所有あるいは配偶者と2人の共有にかかるものであること
- 当該建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈または死因贈与がされたこと
以上の要件が必要です。
また、配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間とされています(遺産分割の協議や調停もしくは遺言において、終身ではない存続期間を定めることもできます。家庭裁判所が遺産分割の審判において存続期間を定めることもできます。ただ、存続期間の延長や更新はできないことになっています)。
配偶者居住権に基づき使用収益等ができますが、配偶者居住権の譲渡をすることは、できません。
このように、配偶者居住権については、配偶者であれば誰でも利用できるというわけではなく、また利用する場合においても、一定の義務があります。また、配偶者居住権の価値の評価も、簡単ではないと思われます。
さらに、この制度が利用可能な場合に当たるとしても、必ずしも利用することがふさわしいケースとは限りません(例えば、すぐに施設入居を検討したり、自宅売却を希望したりする事態が生じる可能性もあります)。利用を検討される際には、専門家に相談されることをお勧めします。
なお、配偶者居住権に関する規定は2020年4月1日から施行されますので、同日以降に発生した相続に関して適用されます。また、同日前にされた遺贈について、改正相続法の適用はないとされています(附則10条)ので、配偶者居住権を設定するという遺言は、同日以降の作成である必要があります。
(2)配偶者短期居住権(民法第1037条)―配偶者の居住権を短期的に保護するための方策
被相続人が死亡した場合でも、配偶者は、それまで居住してきた建物に引き続き居住することを希望するのが通常であり、特に配偶者が高齢者である場合には、住み慣れた居住建物を離れることは大変負担が大きいと考えられます。
この点、現行制度の下においても、最判平成8年12月17日の判例法理により、配偶者が相続時に被相続人の建物に居住していた場合には、特段の事情のない限り、被相続人と相続人との間で、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたと推認するとして、配偶者は遺産分割が終了するまでの間、短期的な居住権が確保されるという保護が図られていました。
しかし、第三者に居住建物が遺贈されてしまった場合や被相続人が反対の意思を表示した場合には、使用貸借が推認されず、居住が保護されないということになり、配偶者の保護ができませんでした。
そのため、配偶者が相続開始時に被相続人の所有する建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、一定の要件の下に、一時的な法定の居住権が設定されるという配偶者短期居住権の制度を新設し、被相続人が居住建物を遺贈した場合や、反対の意思を表示した場合であっても、配偶者の居住を保護することができるようにしたものです。
また、常に最低6か月間は、配偶者の居住が保護されることとなります。
配偶者短期居住権は、(1)でご説明した配偶者居住権(民法1028条1項)と同じく配偶者が居住建物を無償で使用できる権利ですが、配偶者居住権と異なり、配偶者は、一定の要件を満たせば法律上当然に配偶者短期居住権を取得することになります(遺言、遺産分割などによる必要がありません)。
また、取得した短期配偶者居住権について、遺産分割において配偶者の具体的相続分からその価値を控除する必要は、ありません。
<さいごに>
配偶者の居住権を保護するための、以上の方策については、あくまでも法律婚(婚姻届を提出した夫婦)に適用されるものであり、事実婚の夫婦には適用できません。
家族には、多様な在り方があり、それは現代社会の中で十分に尊重されていくべきものであるところ、相続法改正についても、今後、さらなる検討がされていくことが必要であると思います。
| 【参考】
(配偶者居住権) (配偶者短期居住権) |
この記事の担当者

- 気軽にご相談いただくことにより、紛争の発生、拡大を防止できることがあります。「こんなこと相談していいのかな?」と迷われている方にとって、相談しやすいと思っていただける、そして、相談して良かったと思っていただける弁護士でありたいと思っております。
ブログ更新履歴
- 2025年2月12日スタッフブログインタビュー 戦争体験を語り継ぐ 名古屋空襲体験者 服部 勝子(はっとり かつこ)さん
- 2024年12月23日スタッフブログ選択的夫婦別姓
- 2024年3月25日スタッフブログ相続学習会を開催しました
- 2022年12月28日スタッフブログ離婚-その種類や手続に関する基本的な知識について