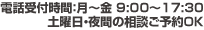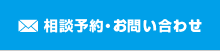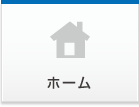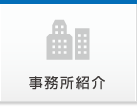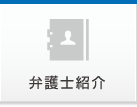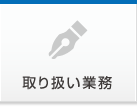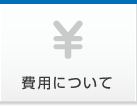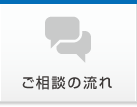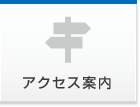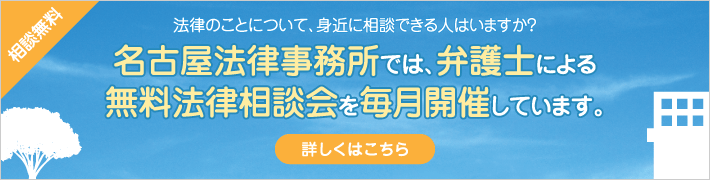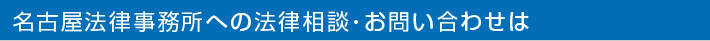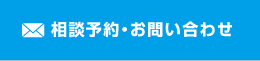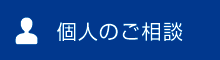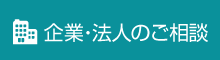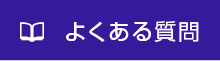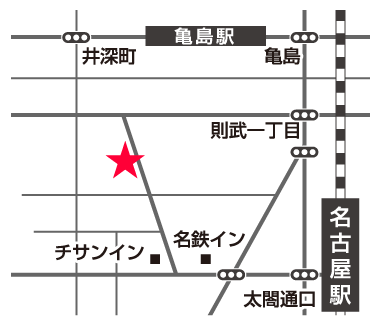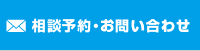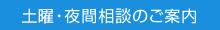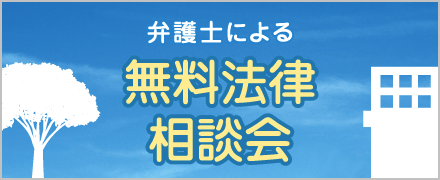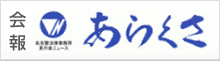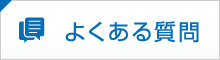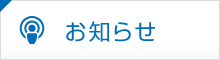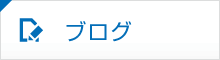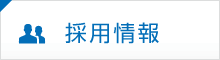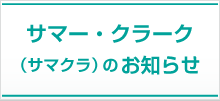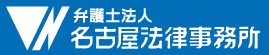スタッフブログ
選択的夫婦別姓
弁護士 兼松 洋子
選択的夫婦別姓制度について、ご存知でしょうか。
どのような制度なのか、なせ必要なのか、解説してみたいと思います。
1 婚姻に際して夫婦の同姓が強制されている
現在、我が国では、全ての夫婦に対し、婚姻に際していずれか一方が改姓して夫婦が同姓となることを義務づけており、双方がともに婚姻前の姓を維持したままで婚姻することは出来ません(夫婦同姓制度)。
どのような法律によるのかというと、民法第750条です。同法は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めています。
したがって、結婚(法律婚)するためには、双方ともに自分の自己の姓(名字)をそのまま維持したいと希望していたとしても、どちらか一方が、姓を変えない限りは結婚できません。
このような夫婦同姓の強制は、男女平等を助長しているという点および人格権たる氏名権を侵害するという点から問題があります。実際、世界の国々においても氏選択の権利を尊重するための法改正がなされ、夫婦同姓を法律で義務づける国は日本のほかにはないという状況となっています。
1996年には法務大臣の諮問機関である法制審議会が、選択的夫婦別氏制度を導入する「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申しました。
しかし、今日に至るまで一度も法案提出すらされないままであり、選択的夫婦別姓制度の導入が実現されないままに、既に1996年の答申から四半世紀以上が経過してしまっています。
2 選択的夫婦別姓制度とは何か
選択的夫婦別姓制度とは、結婚にあたり、それまでの姓をそのまま維持することも、配偶者の姓に改姓することも、いずれでも選択できるようにする制度です。選択的ですので、夫婦で同姓になることも、各自がそれまでの姓を維持することも、それぞれの夫婦において選択することができ、どちらの意思も尊重することができるという制度です。
3 夫婦同姓を強制する民法第750条が憲法に違反していること
選択的夫婦別姓制度を導入するということは、民法第750条を改正するということですが、そもそも同法が憲法に違反していて、改正が必要であるということについて、触れていきたいと思います。
(1)憲法第13条違反
氏名は、生まれたときから婚姻のときまで継続して使用していることによって、その人の人格に密接に結びつくばかりではなく、社会活動における信用とも大きく関わってくるものです。NHKが在日韓国人本人の申し入れにもかかわらず、その氏名を日本語読みにしたことの違法性が問題になった事案(1988年2月16日最高裁判決。)において、判決理由中で、「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば。人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するものというべきである」としています。意に反して氏名の強制をされない自由もまた、人格権の重要な一内容として憲法第13条によって保障されるものです。
夫婦同姓を義務づける民法第750条は、婚姻に際して姓を変更したくない人の意に反して改姓を強制し、氏名の変更を強制されない自由を不当に制限するものですので、憲法第13条に反しています。婚姻の際に、意に反して改姓をよぎなくされた人は、自分自身を失った感じや人格を否定されたような苦痛を感じたり、社会的経済的不利益を被ることによる精神的苦痛を受け続けることになってしまっています。
また、婚姻するかしないか等を決定することは、個人が自律的に生存するために最も重要で本質的な権利の一つであり、婚姻の自由は憲法第13条の自己決定権として保障されるものです。
夫婦が同姓にならなければ婚姻できないとすることは、この婚姻の自由を不当に制限するものなのです。
(2)憲法第14条違反
夫婦となろうとする2人が、ともに婚姻前の姓を維持したままであろうとしても、法律上の夫婦となるためには、その生き方や信条に反して夫婦同姓を選択しなければなりません。生き方や信条を貫くならば法律上の婚姻はできず、その結果、婚姻の法的効果受けらないことになってしまいます。このような差別的取扱いすることとなる、夫婦同姓を義務づけている民法第750条は、憲法第14条に反しています。
(3)憲法第24条違反
憲法第24条第1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と定め、同条第2項は、「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」として、婚姻における人格的自律権の尊重と両性の本質的平等を定めています。
民法第750条は、婚姻に「両性の合意」以外の要件を不当に加重し、当事者の自立的な意思決定に不合理な制約を課すものです。
また、新たに結婚をする夫婦のうちの約95%で女性の方が姓を変えており、事実上、多くの女性が改姓を強いられている現実があり、両性の本質的平等に反するものとなっています。
したがって、民法第750条は、憲法第24条に違反しています。
4 最高裁の判断
最高裁は、2015年12月16日の判決や2021年6月23日の決定で、民法第750条を憲法に違反するとは判断しませんでした。
しかし、これらの判断は、選択的夫婦別姓制度の導入を否定したというものではありません。
2015年最高裁判決は、その多数意見において、婚姻に伴う改姓が女性に対して特に不利益を生じさせていることを認め、選択的夫婦別姓制度の導入については、これを否定せず、「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄」として、国会での議論を促しています。
2021年最高裁決定も、「夫婦の氏についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題と、夫婦同氏制を定める現行法の規定が憲法第24条に違反して無効か否かという憲法適合性の審査の問題とは、次元を異にするものである」として、2015年判決と同様に国会での議論を求めています。
5 夫婦同姓を法律で強制しているのは日本だけ
以前には日本以外にも夫婦同姓を強制する国がありましたが、国連女性差別撤廃委員会による勧告の影響などもあって、諸外国では20世紀中に法改正が進み、現在、夫婦別姓を認めていないのは日本だけとなっています。
日本も、国連女性差別撤廃委員会から2003年以降2024年までに4度にわたり、結婚に際し旧姓を維持することを選択できるようにする法改正についての勧告を受けています。
6 いわゆる通称使用だけでは限界がある
通称使用ができる場面を増やしていけば不利益はなく、別姓を認める必要はないのではないかという意見もあるかもしれません。
しかし、通称は、あくまでも「通称」であり、戸籍制度に基づく法律上の氏名ではないことから限界があります。確かにマイナンバーカード、運転免許証、住民票、パスポートなどへの旧姓の併記が実現していますが、「通称」での金融機関との取引や携帯電話契約、国際航空券の購入、出入国などは、非常に厳しく制限されており、国際的には、マネーロンダリング、テロ資金供与等の対策の観点から厳格な本人確認が求められており、「通称」での金融機関の取引や携帯電話の契約、国際航空券の購入、出入国などは、厳しく制限されています。納税や登記(会社設立・役員就任、不動産取引)など、社会経済活動の基礎となる重要な場面で、旧姓の併記が認められたものの、通称名との同一性の証明のために。本来であれば不要な個人情報の開示を余儀なくされ、それ自体が精神的苦痛を伴うものです。
仕事や研究等で築いた信用や評価を損ない、キャリアが断絶されてしまうなどの不利益も深刻です。
また、今でも多くの人が、通称使用を職場や親族に認めてもらうことの困難さに悩んでいます。
通称は、やはり通称にすぎず、「通称」を使用しなければならない苦痛が続くことを解決できないのです。
この記事の担当者

- 気軽にご相談いただくことにより、紛争の発生、拡大を防止できることがあります。「こんなこと相談していいのかな?」と迷われている方にとって、相談しやすいと思っていただける、そして、相談して良かったと思っていただける弁護士でありたいと思っております。
ブログ更新履歴
- 2025年2月12日スタッフブログインタビュー 戦争体験を語り継ぐ 名古屋空襲体験者 服部 勝子(はっとり かつこ)さん
- 2024年12月23日スタッフブログ選択的夫婦別姓
- 2024年3月25日スタッフブログ相続学習会を開催しました
- 2022年12月28日スタッフブログ離婚-その種類や手続に関する基本的な知識について