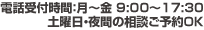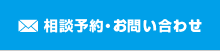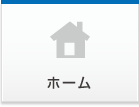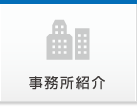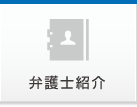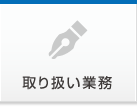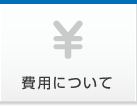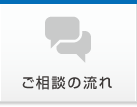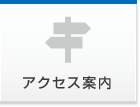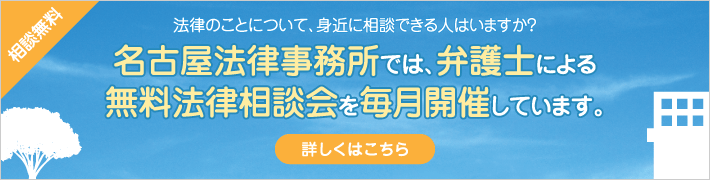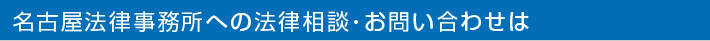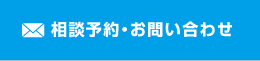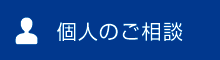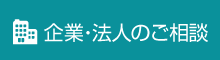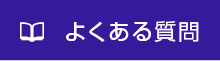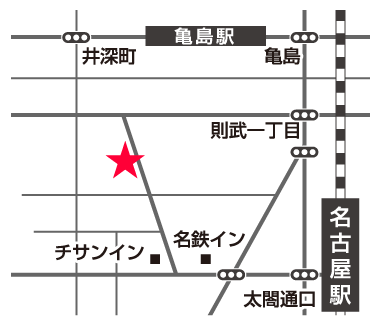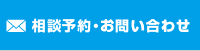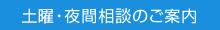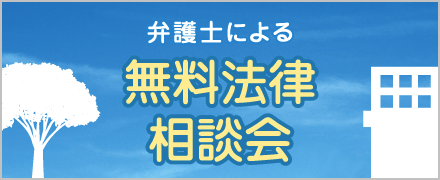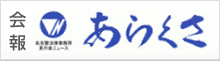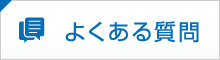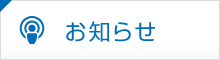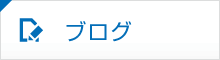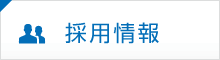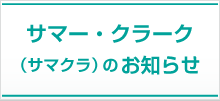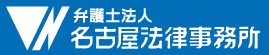憲法
インタビュー 戦争体験を語り継ぐ 長崎被爆者 木戸季市さん
広島、長崎の原爆被爆者で作られている日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会)の事務局長を務めている木戸季市さんは岐阜にお住まいです。当事務所が原爆症認定訴訟の事務局を務めていたことから、木戸さんとは親しく交流しており、2018年には事務所総会で講演をしていただいたこともあります。
被爆から77年を迎えた被爆者の思い、木戸さんの原爆体験などについてお話を伺いました。聞き手は樽井弁護士。
─核兵器禁止条約の第1回締約国会議に参加されましたが、いかがでしたか。
オーストリア政府主催の「核兵器の非人道性に関する国際会議」でスピーチをしました。いかに原爆が反人間的に命を奪ったかと、日本が条約に署名、批准しないのは、戦争犠牲受忍論(注1)を政策の基本としているからだということを話しました。
原爆は人間が人間らしく生きることを許さない反人間性のものだということを実感しています。
─反人間性?
そう。非人道性というよりも反人間性。
僕は長崎の爆心地から2㌔で被爆しました。5歳でした。前日に母の実家の鹿児島県の出水から、母と帰ったばかりでした。僕があまりに小さいので、母は疎開を見送ったのです。おやじは「空襲が激しくなってきたから長崎に帰るな、と手紙に書いただろう」と怒った。しかし、その手紙は郵便が遅れていて、着いていないわけです。
あの日、8月9日、家のすぐ前の道路で、配給のために母親たちが集まっていた。僕はお袋を追って走り出た。飛行機の音が聞こえた。あるお母さんが長崎弁で、「おかしかね。アメリカん、飛行機んござる。元気のよかもん」と言った。飛行機の音が、元気がいいと。その瞬間、ピカ!ドン! 近いから時差なく、まさにピカドンなの。
「いっちゃん!」と名前を呼ぶ母の声で気がついたら、爆風で20メートルぐらい飛ばされていた。たぶん母が僕を抱いて防空壕まで逃げた。僕は顔半分、母は顔と胸をやけどした。母は動けなくなり、顔がはれ上がって目が開けられなくなった。
8人きょうだいの末っ子です。本当は9人なんだけど、僕のすぐ上が生後一カ月もたたずに亡くなった。一番上の兄は海軍兵学校、2、3番目の兄は出水に学童疎開していて、被爆していない。一番上の姉も結婚して鹿児島にいた。
2番目の姉は爆心地から1・2㌔の国民学校で被爆した。教員でした。運動場にいた人は亡くなり、姉は中庭の倉庫の中にいたから、光を浴びていない。そのかわり、体のあちこちにガラスが突き刺さった。3番目の姉は爆心地から3・5㌔の勤め先の三菱造船所の事務所にいた。4番目の姉は、まだ女学生で自宅にいたから光を浴びていない。家は全焼しました。
夕方だと思うが、おやじが防空壕に来て、最初の言葉が忘れられない。「ああ、みんな無事で良かった」と。お袋が大やけどをしているのに。それまでにおやじが何を見てきたかということです。生きている、それだけで、無事で良かったと。
翌日、父が勤めていた木材店が所有する家に家族で逃げた。僕は、土を運ぶ籠に乗せられ、母は戸板に寝かされて運ばれた。街は真っ黒だったという記憶が残っている。

その後、占領軍が来たら女性が暴行される、という噂が立って逃げることになった。母は動かせない。父は看病。それで、姉3人と僕が出水に行くことになった。汽車は超満員。遅々として進まない。2番目の姉はまだガラスが体に入っていた。鹿児島にたどり着けたとしても、だれか亡くなるかもしれない。どうせ亡くなるなら、両親と一緒にいる方がいいよね、ということで死ぬ覚悟で諫早から長崎に引き返した。帰る列車はガラガラなの。その中に僕の記憶では引き揚げの海軍の軍医がいた。僕のやけどを見て、「いい薬がある」と、治療をしてくれた。母の話をしたら、残った少ない薬を持たせてくれた。
肥田舜太郎先生(注2)が、被爆者の生と死を分けたものとして3つの条件を挙げています。体を休めるところがあったか、食べ物があったか、治療を受けられたか。それが生死を分けたと。そして、その後の健康、生活も大きく左右された。だから、偶然ではあるけれど、私は家があり、食料があり、治療を受けられた。「恵まれた被爆者」としか言いようがない。
あのときは、何が起こったかはわからなかった。ただ、こんなことは起こってはいけないというのは思いました。それは、この77年変わっていないですね。従軍カメラマンの山端庸介さんが撮った子どもが真っ黒になって死んでいる写真じゃないけれども、いまだに思い浮かびます。エビ型になって、頭に穴がぽんと開いたとかね。
家族で被爆の話は全くしなかった。やっぱり耐えられないのかな。人間でなくなるような。
─木戸さんはこれまで、自分は一番小さかったから記憶があまりなくて、とおっしゃっていたので、被爆の話を詳しく聞いたことがありませんでした。核不拡散条約(NPT)再検討会議があったニューヨークはどうでしたか。

「原爆展」開幕式で発言する木戸氏
大きかったのは国連原爆展です。2005年、10年、15年、そして今回が4回目です。パネル製作委員会を被団協の中に作り、5年がかりで準備しました。国連とも議論して合意の上でパネルを作ります。回を重ねるごとに内容が良くなり、国連との信頼関係も深まっています。
今回はNPT再検討会議の議長がテープカットする予定でしたが、手違いで時間に来ない。時間をつなぐために私が被爆体験を話したら、会場に着いた議長が話をずっと聞いていた。被爆者の話を直接聞いたのは初めてだそうです。被爆者が直に話さないといけない、まだ話し足りないと思いました。NPT再検討会議が終わった後のマスコミの論調が気になりました。
─決議が採択できなかったことですね。日本のマスコミは「最後にロシアが反対したから」と。
それは事実だけれど、NPTの機能がマヒしたかのように言っているのは間違いです。NPTの存在はますます重要になってきている。圧倒的多数の国が核兵器禁止条約の上にNPTを位置付けている。あるいはNPTの上に核禁条約が生まれているので、まさに一体です。私の感じでは、機能マヒというのは、核兵器保有国が追い詰められているから、必死になって巻き返そうとして言っている。議長が妥協に妥協を重ねて合意できる文書を作るのに対して、核兵器保有国が抵抗していたのですよ。
─2022年最大の国際政治上の事件はウクライナ侵攻だと思います。ロシアが核兵器の使用を脅迫に使いました。
権力者だろうが、核兵器を使って人類の歴史を抹殺することは絶対に許されない。誰にもその権利はないと思う。ロシアに最大の責任があるのはもちろんだが、アメリカをはじめ西欧諸国にもウクライナ戦争を止めさせようと努力している姿勢が感じられない。被団協とか被爆者は、武力で解決するのではなく、対話で解決することを主張してきたし、その感を強くしています。対話とは、人間が人間になるための基本的な行為です。今、対話をしている国がどこにあるでしょう。
ウィーン、ニューヨーク行動で、憲法9条は改めてすごいと感じました。戦後の日本は戦争で一人の命も奪っていないし、奪われていない。憲法9条の基本は対話だから、9条を世界の規範にして、戦争も核兵器もない世界を実現することが我々に課せられているのではないかと強く感じました。

木戸季市さんプロフィール
1940年長崎市生まれ。1969~2003年岐阜聖徳学園大短期大学部教員。現在名誉教授。
1991年岐阜県原爆被爆者の会(岐朋会)を結成、事務局長に就任。
2017年から日本原水爆被害者団体協議会(被団協)事務局長
*注1 戦争犠牲受忍論
「戦争損害は国民のひとしく受忍しなければならないものであって、これに対する補償は、憲法の全く予想しないものである」という判例法理。戦後補償訴訟において、国は、しばしばこの法理に基づいて国に法的責任がないことを主張して戦争被害者の請求を退けてきた。
*注2 肥田 舜太郎(ひだ しゅんたろう、1917年|2017年)医師。広島の原子爆弾投下直後から被爆者救援・治療にあたった。自身も被爆者でありながら被爆者の診察を続け、被爆の実相を語り、核兵器廃絶を訴えた。
この記事の担当者

-
弁護士は、様々な相談事やトラブルを抱えた方に、法的な観点からアドバイスを行い、またその方の利益をまもるために代理人として行動します。私は、まず法律相談活動が弁護士として最も重要な活動であると考えています。不安に思っていたことが、相談を通じて解消し、安心した顔で帰られる姿を見ると、ほっとします。
また、民事事件、刑事事件など様々な事件を通じて、依頼者の立場に立って、利益を実現することに努力します。同時に、弁護士としての個々の事件を通じて、社会的に弱い立場にある方の利益を守ったり、社会的少数者の人権を擁護することを重視しています。
そのような観点から、弁護士会や法律家団体などでの活動にも取り組んでいます。
ブログ更新履歴
- 2025年2月13日スタッフブログ大垣警察~市民監視事件控訴審で画期的な勝訴判決~
- 2024年10月15日スタッフブログ日本被団協にノーベル平和賞
- 2024年1月21日個人の労働問題解決事例をご紹介 こんなお困りごとありませんか?-労働-
- 2023年12月21日スタッフブログストライキについて