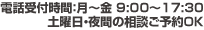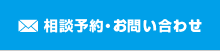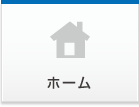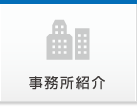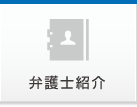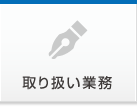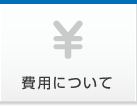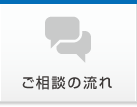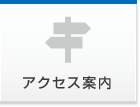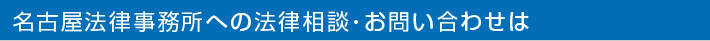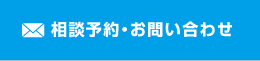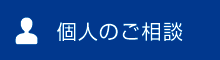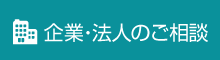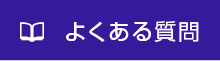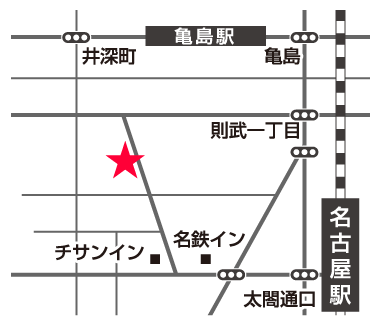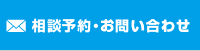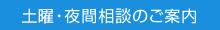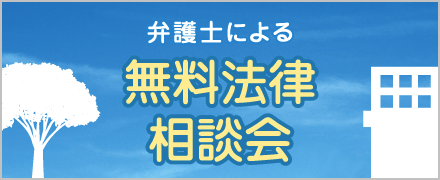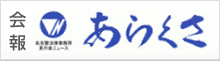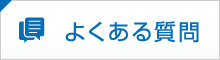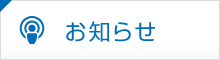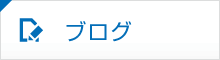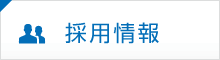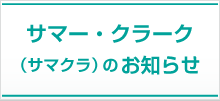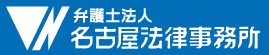離婚
- 「離婚の話がでていますが、離婚したくありません」
- 「離婚をしたいけれど、相手が話し合いに応じてくれません」
- 「相手が浮気をしているので、浮気相手に対して慰謝料を請求したい」
- 「離婚にあたって、夫婦の財産をどう分けるかで話がまとまりません」
- 「現在別居をしていますが、生活費はどうなるのでしょうか」
- 「話し合いで離婚はしたのですが、後から夫婦の財産を分けることを請求できますか」
- 「離婚をした後に、約束した養育費を支払ってもらえません」
- 「自分が浮気をして別居してしまったのですが、こちらから離婚できますか」
結婚はしたものの、様々な事情で夫婦関係に問題が生じることも少なくありません。
時には、それが離婚につながることもあります。
離婚には、離婚原因、慰謝料、財産分与、養育費、親権、面会交流権など様々な法的問題がついて回りますが、お互いの感情のもつれが邪魔をして冷静な話し合いができないかもしれません。また、日常の力関係から思うような話し合いができないこともあると思います。
そこで、専門家である弁護士が間に入って離婚問題の解決にあたります。当事務所には、経験豊富な弁護士、女性の弁護士なども在籍しておりますので、安心してご相談ください。
1 離婚について
以下の説明の通り、夫婦間で協議が整えば離婚できますが、合意できない場合は離婚調停を起こし、それでも合意できない場合は離婚裁判を起こすことになります。最終的に裁判で離婚が認められるかどうかは、法的な問題です。ところが、夫婦間では、ついつい感情的になってしまいます。「離婚ができるのか」「離婚しなくてもいいのか」については、法律の専門家である弁護士に相談することが解決の糸口になります。
⑴ 離婚の方法
離婚をするには次のような方法があります。
| 協議離婚 | 裁判所を介さずに当事者間の話し合いで離婚をする方法です。 |
|---|---|
| 調停離婚 | 家庭裁判所の調停手続を利用した話し合いで離婚をする方法です。 |
| 裁判離婚 | 調停でも話がまとまらない場合に、家庭裁判所に訴訟を起こして離婚する方法です。離婚については、原則として調停をしてからでないと裁判を提起できません。 |
※この他にも調停がまとまらない場合には審判離婚という方法もあります。
(2) 離婚の理由
裁判で離婚が認められるには、次のような理由が必要になります。一方で、協議離婚や調停離婚ではこのような理由がなくても夫婦双方が合意すれば離婚ができます。
- 相手が不貞行為をした場合
- 相手から悪意の遺棄をされた場合
- 相手の生死が3年以上不明である場合
- 相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
- その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合
<弁護士費用> 離婚
(1)着手金…ご依頼時にお支払いいただく費用です。
| ご 依 頼 内 容 | 着 手 金 |
|---|---|
| 交 渉 | 10~30万円 |
| 調 停 | 20~40万円 |
| 訴 訟 | 20~50万円 |
※交渉から調停へ、調停から訴訟へ移行する場合の追加着手金は、上記の金額から減額させていただく場合がございます。
(2)報酬…ご依頼の件が成功した際にお支払いいただく費用です。
| 成功内容 | 報 酬 |
|---|---|
| 離 婚 | 20万円~40万円 |
| 養 育 費 | 上限7年分×10% |
| その他の財産上の請求 | 経済的利益(※)の4~16% |
※経済的利益とは、ご依頼者様が弁護士に依頼された案件が解決した場合にご依頼者様が得られる利益をお金に換算したものです。
- 年金分割を附帯請求した場合でも着手金・報酬はいただきません。
- 親権、面会交流その他で成果を得た場合には2〜10%程度報酬を加算させていただくことがあります。
弁護士費用の算定例
<ケース1>
- 協議離婚の交渉を依頼し、交渉によって協議離婚が成立した。
<着手金>
30万円
<報酬金>
30万円
<ケース2>
- 協議離婚の交渉を依頼したが、交渉によっては離婚が成立せず、調停によっても成立せず、訴訟によって離婚が成立した。
<着手金>
30万円(交渉と調停分)+20万円(訴訟移行分)
<報酬金>
40万円
注1)離婚のみが成果として得られた場合の算定例です。お子様の養育費の請求が認められた場合や、財産分与によって財産を獲得した場合、慰謝料の請求が認められた場合は、報酬金が別途発生します
注2)上記の算定例はあくまでも目安であり、事案の内容によって金額は上下しますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。
2 お子さんについて
大切なお子さんのことになると、ついつい想いだけが先行してしまいがちですが、お子さんに関する問題は、お子さんへの想い+法的な視点からお子さんのためになるかどうかが重要になってきます。お子さんへの想いをたしかなものにするためにも、弁護士に相談することが大切になってきます。
(1) 親権
離婚をするにあたっては、未成年のお子さんがいる場合、夫婦のどちらを親権者とするかを決めないといけません。お子さんの成長に関わる重要な問題ですので、この親権者を裁判で決める場合には、養育環境、経済力、お子さんの意思などを総合的に考えて決めることになります。
また、離婚をする前に夫婦が別居をしている場合、実際にどちらがお子さんの監護をするのかについて問題になる場合もあります。
(2)面会交流
離婚によって親権を失った場合でも、お子さんに会えなくなるわけではありません。お子さんに会って、会話をしたり、一緒に遊んだりする権利が認められています。これを面会交流権と言います。
そもそも面会交流を認めるのかどうか、認められる場合は面会交流の場所や回数、日時などを、お子さんの意思やお子さんに与える影響など様々な事情を考慮して決められます。
この面会交流に関する問題は、離婚前に別居をしている場合にお子さんの監護を行う者を決めていた場合にも問題になります。
<弁護士費用> 面会交流等
(1)着手金…ご依頼時にお支払いいただく費用です。
| ご 依 頼 内 容 | 着 手 金 |
|---|---|
| 調 停 | 15~25万円 |
| 審 判 | 15~25万円 |
※交渉から審判へ移行する場合の追加着手金は、上記の金額から減額させていただく場合がございます。
(2)報酬…ご依頼の件が成功した際にお支払いいただく費用です。
報酬 : 15~25万円
弁護士費用の算定例
<ケース1>
- 離婚と同時にお子様の親権を争い、調停では成立せず、訴訟によって離婚が成立し、お子様の親権も獲得できた。
<着手金>
30万円(調停分)+20万円(訴訟移行分)
※離婚事件の着手金を含みます
<報酬金>
40万円(離婚成立分)+25万円(親権獲得分)
<ケース2>
- 既に離婚は成立していて、元妻が親権者となっているお子様との面会交流を求めて調停を申立てたが、調停では成立せず、審判によって面会交流が認められた。
<着手金>
15~25万円(調停分)+15~25万円(審判分)
<報酬金>
15~25万円
注1)離婚と同時に親権や面会交流を争った場合は、その着手金は離婚を依頼した着手金に含まれますので、別途の着手金は発生しません。
注2)上記の算定例はあくまでも目安であり、事案の内容によって金額は上下しますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。
3 離婚に関係するお金の問題
お子さんの養育費、財産分与など離婚に関係するお金の問題は、法的な基準と提出される資料によって計算されますので、冷静な分析・判断が必要になってきます。
⑴ 婚姻費用
(特に離婚する前に別居をしているときに)相手に収入があるのに生活費を負担してくれない場合には、相手方に婚姻費用(生活費)の請求をすることができます。
この婚姻費用は、衣食住の費用、お子さんの養育にかかる費用、お子さんの人数、夫婦それぞれの収入状況に応じて計算がされます。
婚姻費用については、計算方法をはじめ過去の婚姻費用の請求ができるのかなど、様々な問題があります。
⑵ 養育費
離婚後にお子さんの養育費についてどのように分担するかは大きな問題です。この養育費についても、お子さんの養育にかかる費用、お子さんの人数、夫婦それぞれの収入状況などを考慮して計算されます。
⑶ 財産分与
結婚後に築いた財産は,形式上夫婦のどちらかの単独名義になっていても,夫婦共同の財産として財産分与の対象となります。
財産分与については、どこまでの範囲が夫婦共同の財産なのか、自動車や不動産のローン残額の方が評価額を超える場合にも対象となるのかなどの問題があります。
財産分与については、離婚した後に行うこともできますが、離婚成立から2年の経過で家庭裁判所の審判を受けることができなくなってしまいますので、注意が必要です(話し合いで決めることはできます)。
⑷ 年金分割
厚生年金または共済年金について,婚姻期間中の年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割することができます。
ただし,基礎年金部分などは対象にならないなど分割できる範囲に制限がある点や離婚成立から2年が経過することで分割できなくなる点などについて注意が必要です。
⑸ 慰謝料
離婚の原因が相手の不貞行為や暴力などの場合、相手に対して慰謝料などの損害賠償請求することができます。
<弁護士費用> 慰謝料請求
(1)着手金…ご依頼時にお支払いいただく費用です。
| ご 依 頼 内 容 | 着 手 金 |
|---|---|
| 交 渉 | 10万円 |
| 訴 訟 | 20万円~40万円 |
※交渉から調停へ、調停から訴訟へ移行する場合の追加着手金は、上記の金額から減額させていただく場合がございます。
(2)報酬…ご依頼の件が成功した際にお支払いいただく費用です。
報酬 : 経済的利益の10~16%
弁護士費用の算定例
- 配偶者が不貞行為を行ったので、配偶者と不貞行為をしたXに慰謝料を請求したい。
最初は交渉を試みたが、決裂したため、訴訟を提起し、慰謝料が合計で200万円を得ることができた。
<着手金>
10万円(交渉)+20万円(訴訟)-5万円(減額)=25万円
<報酬金>
200万円(経済的利益)×16% =32万円
養育費の金額などを決めても、その後の収入や子どもの教育費の状況によって金額などを変更する必要がある場合もあります。
そんなときには、養育費の額などの変更について調停を行うことで、その後の状況に応じた柔軟な解決をすることもできます。
4 法テラスによる弁護士費用援助について
法テラスは弁護士費用などを支払う余裕がないという方に対して、その費用を立て替える制度があります。
無料の法律相談を受けた結果、弁護士費用等の援助(代理援助・書類作成援助)の要件を満たす場合には、費用立替制度を利用することができます。
援助開始決定後、弁護士の選任手続きを行い、法テラスと案件を担当する弁護士と本人の三者間で所定の契約書を締結します。
これにより、契約書記載の費用や着手金は、法テラスが弁護士に立て替え払いします。立て替えられた費用は、ご依頼者様が法テラスに対して分割等の方法で償還していただきます。
詳しくは、法テラスのウェブサイトをご覧ください。
https://www.houterasu.or.jp/