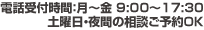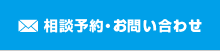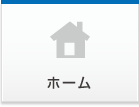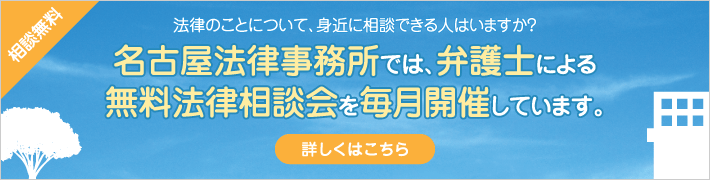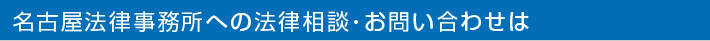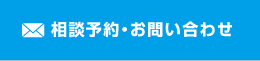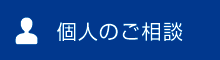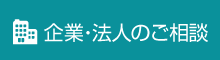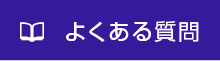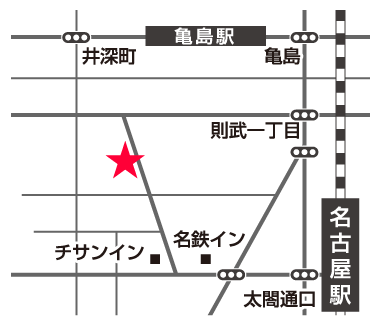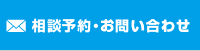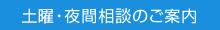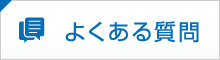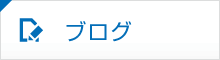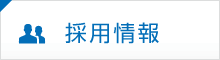スタッフブログ
養育費・婚姻費用の新算定表 最高裁が発表
はじめに
2019年12月23日、最高裁判所が、養育費や婚姻費用を決める際に使われる算定表を更新し、公表しました。2003年に初めて算定表が公表されてから実に16年ぶりの更新で、生活にかかる費用が増えていることなど社会情勢が変化していることが考慮されたとのことです。
皆さんの中にも、更新前の算定表(以下「旧算定表」と言います)に基づいて婚姻費用や養育費の取り決めをし、別居中の夫や離婚した元夫からの支払いを受けている方もいらっしゃるでしょう。一方で、本当であれば養育費や婚姻費用の支払いを受けられる立場にあるのに、そのことを知らず、苦しい生活を余儀なくされている方もいらっしゃるかも知れません。
そこで今回は、養育費と婚姻費用についての基礎知識をおさらいして算定方法をご説明するとともに、今回発表された算定表(以下「新算定表」と言います)についての注意点をご紹介していきます。
基礎知識 ―― 養育費と婚姻費用
養育費とは、「子の監護に要する費用」(民法766条1項)、すなわち、離婚後に子どもの面倒を見ることに決まった親(監護親と言います)に対して、子どもの面倒を見ない親(非監護親と言います)が支払うべき子どもの養育に要する費用のことです。
婚姻費用とは、「婚姻から生ずる費用」、すなわち、結婚している家庭が、その資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用のことで、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生じる費用を分担する」(民法760条)とされています。
法律上の厳密さを無視して分かりやすく言うと、以下のように分けられます。
① 結婚している間は、収入の多い方が収入の少ない方に婚姻費用を支払う。
② 離婚後は、未成年の子どもが居れば、非監護親は監護親に養育費を支払う。
そして、父母双方の収入と子どもの人数・年齢に応じて、婚姻費用・養育費の額は決められることになり、それを簡単に計算できるのが算定表というわけです。
もっとも、算定表だけで全てが決まるわけではなく、個別の事情によって婚姻費用・養育費の額は上下します。例えば、夫が住宅ローンを支払い続けている自宅に妻と子ども達が住み続けている場合、夫が支払うべき婚姻費用の額は算定表よりも下げられることが多いですし、子どもが私立高校に通学していて学費負担が高額な場合、養育費の額は算定表よりも上げられることが多いです。なお、これらの個別事情を説明するとキリがありませんので、詳しく聞きたい方は弁護士にご相談下さい。
その上で、婚姻費用・養育費の額が話し合いで決まらない場合は、最終的には裁判所の決定で額が決められることになり、裁判所で決められた額を支払わない場合は、最悪の場合は給与の差し押さえなどの強制執行を受けることになります。
養育費と婚姻費用の算定方法
いわゆる収入按分型という算定方法が取られていて、具体的には以下の手順で算定されます。
<婚姻費用>
⑴ 義務者と権利者の基礎収入をそれぞれ算定する
→公租公課や通常必要となる経費を差し引いた、生活費として費消される額を算出します。実際には、収入額に応じたパーセンテージで算出します
⑵ 権利者世帯に割り振られる婚姻費用を算定する
→義務者と権利者の基礎収入の合計を、権利者世帯と義務者世帯に按分計算します。その際、親の生活費指数を100として、14歳以下の子どもの指数は62、15歳以上の子どもの指数は85で計算します
⑶ 義務者から権利者に支払うべき婚姻費用の分担額を算定する
→⑵の婚姻費用から、権利者の基礎収入を差し引きます。
<養育費>
⑴ 義務者と権利者の基礎収入をそれぞれ算定する
→婚姻費用の場合と同じ計算です
⑵ 子どもの最低生活費を算定する
→義務者の基礎収入を、義務者と子どもの生活費指数に基づいて按分計算して子どもの最低生活費を算出します
⑶ 義務者の養育費分担額を算定する
→⑵の子どもの最低生活費を、義務者と権利者双方の基礎収入の割合で按分計算し、義務者の負担分を算出します
以下、夫(父)の給与収入が600万円、妻(母)の給与収入が200万円で、16歳と12歳の子どもがいる家庭を例に、婚姻費用と、母が子ども二人の監護親となって離婚する場合の養育費を具体的に算出してみましょう。
<婚姻費用>
⑴ 父の基礎収入:600万円×41%=246万円
母の基礎収入:200万円×43%=86万円
⑵ (246万+86万)×(100+62+85)/(100+100+62+85)=約236万
⑶ 約236万-86万=約150万円(1か月約12万5千円)
※旧算定表では、1か月約11万円でした
<養育費>
⑴ 父母の基礎収入は上と同じ
⑵ 246万円×(62+85)/(100+62+85)=約146万円
⑶ 約146万円×(246万円)/(246万+86万)=約108万円(1か月約9万円)
※旧算定表では、1か月約8万円でした
そして、このような計算過程を省略し、子どもの年齢と人数、父母双方の収入さえ分かればおおよその養育費や婚姻費用の金額が分かるようにしたのが算定表です。
いくつかの注意点
⑴ 成年年齢の引き下げの影響について
2022年4月1日より、民法で定められる成年年齢は18歳となります。これに伴い、養育費の支払いが終わる時期も、現在の20歳から18歳に引き下げられることになるのでしょうか。実際、当事者間で交わした離婚協議書や、家庭裁判所で作成した和解条項で、養育費の終期を「子どもが成年に達する日が属する月」としている例は少なくありませんから、民法の成年年齢の引き下げに伴って養育費の終期も変わると考えるのが自然なようにも思えます。
しかし、今回の新算定表の公表に当たり、最高裁は、民法の成年年齢が引き下げられても養育費の終期が18歳に変わることはないと発表しました。養育費を支払い続けている親御さんには残念な発表かも知れませんが、まだ未成熟で親の養育を必要としている子どもたちにとっては一安心と言えるでしょう。
もっとも、これもケースバイケースで、例えば子どもが高校卒業後に就職し自活できるだけの給料を稼ぐようになったら、養育費を支払う必要はなくなりますので、そのような個別事情がある場合は一度弁護士に相談してみて下さい。
⑵ 既に決まっている養育費等の額への影響について
算定表が変わったことで、既に当事者間の協議や裁判で決められた養育費等の額も変更されるのでしょか。養育費や婚姻費用は、その額を決めた当時の双方の収入や子どもの年齢によって決まっているわけですから、それらの事情が変更した場合は養育費等の額の増減を求めることが出来ます。そうすると、養育費等の算定表が変わったことは、養育費等の額を増減すべき事情の変更に当たるようにも思えます。
しかし、これについても最高裁は、今回の新算定表の公表は、既に決められている養育費等の額を変更すべき事情変更には当たらないと発表しました。
但し、最高裁は、もともと養育費等の額を変更すべき事情変更がある場合は(例えば、義務者の収入が大きく変動した場合など)、新しく養育費等を算定するには新算定表が使われるべきとも発表していますので、諦めるのは早計です。
ここ1~2年のうちに養育費等を決めた場合はともかく、養育費等を決めてから5年以上が経過している場合は、双方の収入や子どもの年齢帯が変更している場合は多いでしょうから、養育費等の増額請求が認められる可能性は十分にありますので、これについても一度弁護士に相談してみて下さい。
この記事の担当者

ブログ更新履歴
- 2023年12月26日その他個人の相談法律相談の活用術
- 2023年9月8日その他友の会第41回総会を振り返る 友の会総会 第2部 記念講演「日本ってどんな国?」~ヤバい日本をあぶり出す~
- 2023年3月3日契約・取引悪質な「暮らしのレスキューサービス」にご注意を!
- 2022年8月16日その他政治と宗教の関係を考える